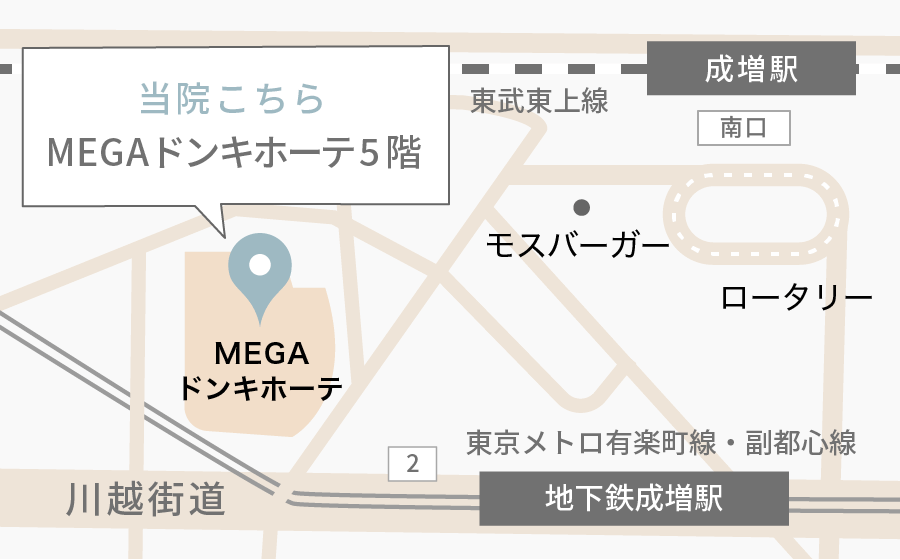イートロスとは?~食べることの重要性
「食べられない」が招く悪循環

イートロスとは、食べる機能が低下し、十分な食事が摂れなくなる状態を指します。単なる食欲不振ではなく、咀嚼(そしゃく)ができない(噛めない、噛みにくい)、嚥下(えんげ)がしにくい(むせる)、消化・吸収がされにくいなど、食べることに関して何らかの問題があることが背景になります。
イートロスは高齢者だけの話ではありません
厚生労働省によると、「65歳以上の高齢者の約8割は何らかのお口の機能障害を抱えている」と言われています。
しかし、若い世代でも、虫歯や歯周病によって抜歯をしたことで、十分に噛めなくなったり、食べ物を飲み込みにくくなったりすることがあります。また、拒食症や過食症などの摂食障害も、イートロスの一因となります。
イートロスは、歯科にとって重要な課題
歯科医師にとって、イートロスは単なる食事の問題ではなく、口腔内の健康や全身の健康状態に悪影響を及ぼす重要な課題です。
イートロスになると、低栄養や脱水症状を引き起こし、免疫力低下や感染症リスク増加などの問題にもつながります。
虫歯や歯周病のリスクが高まったり、口臭や口内炎などのトラブルが発生しやすくなります。さらに誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)などの重篤な病気を招く可能性もあり、最悪の場合、命に関わることもあります。
イートロスの原因

イートロスの原因は多岐にわたりますが、主に以下のことが挙げられます。
口腔内の問題
まず多いのは、歯の喪失や歯周病、入れ歯の不適合などの口腔内の問題です。加齢による筋力低下、骨密度の低下、糖尿病や心臓病などの慢性疾患が背景にある場合もあります。
脳神経疾患
脳卒中やパーキンソン病、認知症やうつ病などが原因になることもあります。認知症やうつ病により、食欲不振や意欲低下、周囲への関心喪失などの症状が現れ、食事を摂ることや、食事内容へのこだわりがなくなり、イートロスになります。
拒食症や過食症
拒食症や過食症、歪んだ体形へのこだわりや極端なダイエットなどが原因で、正常な食生活を送ることができなくなることもイートロスにつながります。
社会的要因
これら病的要因に加え、見逃せないのは社会的要因です。これには独居、孤立、貧困などの生活環境が関係しています。
一人暮らしの高齢者や、経済的困窮で十分な食事が用意できない人、調理設備や食事介助者がいない環境の人などもイートロスのリスクが高くなります。
また、イートロスは、これら複数の要因が複雑に絡み合って起こることもあります。
イートロスを予防するために

まず、「イートロスを知ること」、これが予防の第一歩になります。先ほど述べた内容を知っておくことから全てが始まります。
そして、我々歯科医師は、口腔ケアや栄養管理を通して、イートロスの予防・改善を心がけています。
適切な口腔ケア
虫歯や歯周病の治療、口腔清掃、入れ歯の調整をはじめ、嚥下困難に合わせた補助具の提案をします。お体が不自由な方向けには、訪問歯科診療も行います。
栄養管理
栄養状態の評価、食事指導、栄養補助食品の提案をします。嚥下機能訓練として、嚥下方法の習得、嚥下の改善のリハビリなどを実施します。
小さな頃から虫歯のない環境を作る
歯を失うことでイートロスにならないよう、子供のころから虫歯がない状態を保つことが重要です。お子さんが虫歯にならないようにするには、予防歯科やメインテナンスにより、歯科医院で定期的なチェックを受けるのが大切です。
近年、子供の福祉を充実させる動きもあり、医療費の無料化、もしくは低額で医療が受けられるようになってきています。将来を見据えて、お口をいつも良好な状態にキープできるよう、心がけていきましょう。